医療費の自己負担が高額になったとき
 病気やけがで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担も高額になります。そこで、家計の負担を軽減するため、自己負担が一定額を超えたときに、その超えた額が後日払い戻される「高額療養費」制度が設けられています。
病気やけがで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担も高額になります。そこで、家計の負担を軽減するため、自己負担が一定額を超えたときに、その超えた額が後日払い戻される「高額療養費」制度が設けられています。
なお、この自己負担額から高額療養費として支給される額を控除したあとの額が一定額を超える場合には、一部負担金払戻金、家族療養費附加金または家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
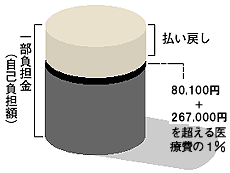 組合員またはその被扶養者が、1ヵ月間に、1つの病院等に支払った額が、一定額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。
組合員またはその被扶養者が、1ヵ月間に、1つの病院等に支払った額が、一定額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。
医療費を計算するときの注意
- 暦月の1日から末日を1ヵ月として計算します。月をまたがって受診した場合は暦月ごとに別計算となります。
- 同じ病院や診療所でも、入院と外来はそれぞれ別に計算されます。
- 同じ病院や診療所で医科と歯科の両方を受診した場合、それぞれ別に計算されます。
- 一部負担金のなかには、入院時の食事代、保険外の費用である特別の病室料や歯科の材料差額などは含まれません。
一定額(自己負担限度額)とは?
| 標準報酬の月額 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 830,000円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 530,000円以上830,000円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 280,000円以上530,000円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 280,000円未満 | 57,600円 |
| 低所得者※ | 35,400円 |
| ※生活保護の被保険者や市町村民税の非課税者等 |
世帯内で合算される場合
同一月内に同一世帯で2件以上、自己負担額21,000円以上を超えるものがある場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えていれば、その超えた額が支給されます。
4回目以降の高額療養費
1年間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上になったとき、4回目からは下表の金額を超えた額が支給されます。
※この場合の1年間とは、常に直近の1年間(12ヵ月)を指します。
| 標準報酬の月額 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 830,000円以上 | 140,100円 |
| 530,000円以上830,000円未満 | 93,000円 |
| 280,000円以上530,000円未満 | 44,400円 |
| 280,000円未満 | 44,400円 |
| 低所得者※ | 24,600円 |
| ※ | 生活保護の被保護者や市町村民税の非課税者等。 |
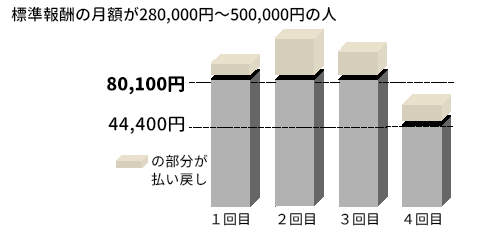
高齢受給者の自己負担限度額
| 所得区分 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| A外来(個人単位) | B入院含む(世帯単位) | ||
| 標準報酬の月額83万以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※140,100円 |
||
| 標準報酬の月額53万以上83万未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※93,000円 |
||
| 標準報酬の月額28万以上53万未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※44,400円 |
||
| 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 ※44,400円 |
|
| 低所得者 | Ⅱ | 8,000円 |
24,600円 |
| Ⅰ | 15,000円 |
||
| ※ | は、多数該当の場合の限度額である。 |
| (注) | 一定以上所得者であっても、その収入額が621万円未満(被扶養者がいない者は484万円未満)である場合は、高額療養費に係る自己負担限度額が「一般」適用となります。 |
特定疾病は10,000円※までの負担
※人工透析を要する標準報酬の月額が530,000円以上の人は20,000円人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は10,000 円(標準報酬の月額が530,000円以上の人は20,000円)となっており、この場合、病院等の窓口での支払いも10,000 円(標準報酬の月額が530,000円以上の人は20,000円)以内で済みます。またこのほか、血友病患者のうち第VIII因子障害、第IX因子障害の人や、後天性免疫不全症候群で血液製剤の投与によるHIV感染者からの2次、3次感染の人についても、自己負担の限度額は10,000 円となっています。
これらの疾病で受診する場合は、共済組合が発行する「特定疾病療養受療証」をマイナ保険証・資格確認書等とともに病院等に提示する必要があります。 該当される方は「特定疾病療養受療証交付申請書」を共済組合に提出し、交付を受けてください。
高額療養費の現物給付について(マイナ保険証または限度額適用認定証)
組合員やその被扶養者(市町村民税非課税の方を除く)が医療機関を受診された場合、マイナ受付ができる医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、限度額適用にかかる受診者本人の情報提供に同意することで、窓口での自己負担額が所得に応じた一定の限度額(高額療養費の自己負担限度額)までとなります。(マイナ保険証をご利用の場合は、当組合へのお手続きは不要です。)
マイナ保険証でなく、限度額適用認定証(紙の認定証)の交付を希望する場合は申請が必要となるため、現職の組合員の方は「限度額適用認定申請書」を勤務先の共済事務担当課にご提出ください(※)。任意継続組合員の方は「限度額適用認定証(任意継続組合員用)」を共済組合へ直接ご提出ください(※)。
なお、組合員の方または組合員の方と全ての被扶養者の方が市町村民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。該当する場合は、現職の組合員の方は勤務先の共済事務担当課にご相談ください。任意継続組合員の方は、共済組合にご相談ください。(「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出せず、マイナ保険証を提示した場合は、窓口での自己負担額が所得に応じた限度額までとなります。)
また、医療機関等窓口で自己負担額が軽減されなかった場合、世帯合算となった場合の高額療養費の差額、附加給付等については、これまでどおり診療を受けた月の早くて3カ月後に自動給付となりますので手続きの必要はありません。
|
| 適用 区分 |
標準報酬の 月額 |
自己負担限度額 |
|---|---|---|
| ア | 830,000円以上 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
| イ | 530,000円以上 830,000円未満 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
| ウ | 280,000円以上 530,000円未満 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
| エ | 280,000円未満 |
57,600円 |
| オ | 低所得者 |
24,600円 |
医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月間が計算期間)の自己負担額の合計額が下表の基準額を超えた場合に支給されます。
| (注) | 自己負担額は高額療養費、高額介護サービス費、家族療養費附加金、公費負担などを控除した後の額です。また入院時食事療養費や保険給付の対象にならないもの(差額ベッド代等)は含みません。 |
合算算定基準額(年額)
| 標準報酬の月額 | 医療保険(共済組合) +介護保険 |
||
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 70歳~74歳 | ||
| 830,000円以上 | 212万円 |
212万円 |
|
| 530,000円以上 830,000円未満 |
141万円 |
141万円 |
|
| 280,000円以上 530,000円未満 |
67万円 |
67万円 |
|
| 280,000円未満 | 60万円 |
56万円 |
|
| 低所得者 | Ⅱ ※1 | 34万円 |
31万円 |
| Ⅰ ※2 | 19万円 |
||
| ※ | 年額は前年8月1日から7月31日の12ヵ月で計算します。 |
| ※1. | 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等 |
| ※2. | 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等 |
支給までの流れ
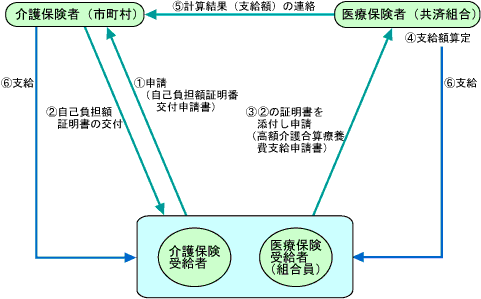
請求に必要な書類
- 「高額介護合算療養費支給申請書」
- 自己負担額証明書(介護保険者から交付されたもの)
高額療養費に関する注意事項
- 高齢受給者証の個人ごとの同一月内の外来自己負担額が外来に係る年間上限額を超えた場合は、組合員からの請求により支給します。