被扶養者
組合員の配偶者や子、また父母など、組合員の収入によって生活している人は、組合員の被扶養者となることができます。
被扶養者と認められた人は、短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められるのは、「主として組合員の収入によって生計を維持」しており、「国内居住要件を満たしている」人のうち、下のいずれかにあてはまる人です。
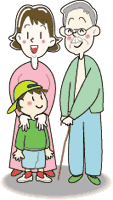 |
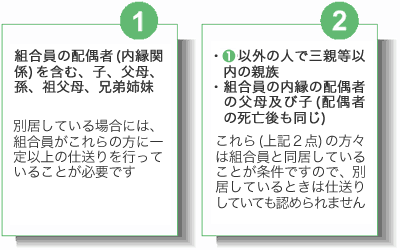 |
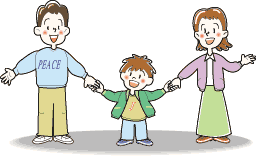
被扶養者とは認められない人
次の場合は被扶養者とは認められません。
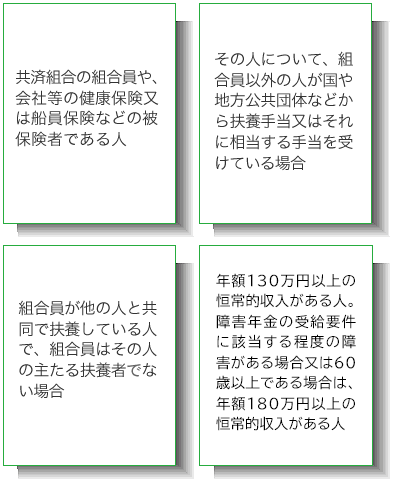
国内居住要件について
被扶養者として認定されるには、日本国内に住所を有している必要があります。(「国内居住要件」)
日本国内に住所を有していない場合、外国において留学をする学生その他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められること(「国内居住要件の例外」)が必要となります。
※令和2年4月1日以降、国内居住要件を満たさず、国内居住要件の例外にも該当しない人は、被扶養者の要件を欠くこととなりますので、被扶養者申告書にて取消手続をしてください。
日本国内に住所を有していることの確認のしかた
住民票で確認します。日本に住民票がある人は、原則として国内居住要件を満たす人となります。
ただし、日本国内に住所があっても、例外として被扶養者から除外される人がいます。
| ① | 海外で就労し、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない人 |
| ② | 日本の国籍を有しない者で、「医療滞在ビザ」で来日した人 |
| ③ | 日本の国籍を有しない者で、「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した人 |
国内居住要件の例外
日本に住民票がなくても、国内居住要件の例外として被扶養者の範囲に含まれるのは次のような人です。
| ① | 外国において留学をする学生 |
| ② | 外国に赴任する組合員に同行する者 |
| ③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 |
| ④ | 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、②に掲げる者と同等と認められるもの |
| ⑤ | ①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
扶養認定における収入の捉え方について
「収入が年額130万円(180万円)未満」の“収入”とは、主なものとして給与収入(給料・賞与・手当等)、社会保障給付金(雇用保険・傷病手当金等)、事業収入(営業収入・農業収入等)、不動産収入、利子・配当収入及び雑収入(年金・恩給・企業年金・農業者年金・個人年金等)などがあります。その他にも恒常的と認められる場合には収入として算定いたします。
収入の判断は年額(130万円未満又は180万円未満)で行いますが、アルバイトやパートなどの給与収入があるときは、年額のほか月額(108,334円[130万円/12月]又は15万円[180万円/12月])でも判断しているため、振り返った1年間の結果として130万円(180万円)以上とならなかった場合であっても、108,334円(15万円)〔月額限度額〕以上となった月から 3カ月平均して月額限度額以上となったときは、年額130万円(180万円)以上見込めるものと判断し、月額限度額以上となった月から取消該当となります。
なお、賞与が支給されている場合は、対象月に案分して判断します。
また、就業初月が月額限度額未満であっても次月以降月額限度額以上の場合は就業日から取消該当となる場合があります。
新たに扶養認定申告を行うときは、扶養の事実が生じた日以降(3ヵ月以上)の収入が月額限度額未満であることが必要です。
なお、雇用保険や傷病手当金などの日額給付となるものについては、給付日数にかかわらず、日額3,612円(130万円/12月/30日)未満であるかどうかで判断します(給付日額×給付日数の額が130万円以上であるかどうかではありません)ので、日額3,612円(130万円/12月/30日)以上の給付である場合は、支給開始日から支給終了までの間取消該当となります。
年額130万円(180万円)については、暦年又は年度によって期間を限定したものではありません。
※扶養認定における収入とは、所得税法上の所得とは同一ではありません。
給与収入については、通勤手当などの諸手当を含み、税や雇用保険等が控除される前の総額となります。
なお、雑収入(年金・恩給・企業年金・農業者年金・個人年金等)にあっては、税や介護保険料及び必要経費等が控除される前の総額となります。
また、事業収入、農業収入、不動産収入等の場合は所得税法上の必要経費控除前の総収入が基本となりますが、扶養認定において必要と認められると判断した経費のみを控除し、その額を収入とします。
夫婦共同扶養(子の主たる生計維持者について)
夫婦が共同して子を扶養している場合は、年間収入見込額が多い方の被扶養者とし、同程度(1割以内)の収入見込額の場合は届出により主として生計を維持し ている方を被扶養者としますが、その子に対する扶養手当が組合員に支給されているときは、扶養手当が支給されている組合員が主たる生計維持者と判断します。
これは、主たる生計維持者の判断であり、これとは別に扶養認定対象者自身が認定要件を備えているかどうかを確認させていただきます。
父母及び祖父母の認定の取扱い
父母・祖父母の双方又は、いずれか一方を被扶養者として認定する場合は、夫婦の扶助義務の観点から、父母・祖父母の年間収入を合算して判断することとします。
なお、祖父母については、父母に扶養義務があるため父母の年間収入や扶養能力、組合員が扶養しなければならない経緯・理由等を勘案し判断します。
また、義父母の認定については、実子に収入がある場合、組合員の収入が多い場合であっても、まずは実子において扶養すべきものとして、慎重に審査することとします。
別居している被扶養者(認定対象者)について
被扶養者と認められるのは「主として組合員の収入により生計を維持している人」です。
このことから、別居している被扶養者(認定対象者)に対しては仕送りを行っていることが必要です。その判定基準は次のとおりです。
1 仕送りの意義
被扶養者の毎月の生活費を援助するものです。そのため、毎月送金があることが必要であり、ボーナス時のみやまとめての送金等、一時的なものは仕送りとはみなしません。
2 仕送り方法
金融機関からの送金のみとします(手渡しによる方法は不可)。
3 確認書類
「仕送り状況申立書」及び銀行の振込受領書やATM利用明細書等とし、受取人と振込人の氏名、日付及び金額が確認できるものとします。
4 仕送り金額
月額5万円以上かつ別居している被扶養者(認定対象者)全員の収入合計の2分の1以上の送金とします。
※ |
別居している者を認定する場合は、原則として上記の取扱いにより行うものですが、当分の間、手渡しによる仕送りも認めることとし、仕送り回数についても数回(隔月又は四半期毎)に分けての仕送りも認めることとします。 |
被扶養者の届出
被扶養者となるには、共済組合の認定を受けることが必要です。 その手続きは「被扶養者申告書」を(所属所長を経由して)共済組合に提出してください。
ただし、その期限は扶養の事実が生じた日(たとえば子供が生まれた日など)から30 日以内となっています。これは、30日以内であれば扶養の事実が生じた日にさかのぼって認定されますが、30日を過ぎてしまうと、届出をした日から認定されるということです。この場合、その間に病気等で受診しても給付は行われず、診療費等は全額自己負担となります。 届出は期限内に済ませるようにしましょう。
認定・取消に必要な添付書類
被扶養者の認定を受けるには、組合員がその人を扶養している事実や扶養しなければならない事情等が確認できる書類が必要です。
なお、被扶養者を取り消す場合には、被扶養者とならなくなった事情等が確認できる書類が必要となります。被扶養者認定・取消の届出の際にこれらを添付して提出してください。
被扶養者申告書の添付書類一覧表(認定時)
被扶養者申告書の添付書類一覧表(取消時)
主な所得を証する書類
※ |
平成20年4月から、新たな医療制度として75歳以上(一定の障害があり、認定を受けた65歳以上の方を含む)の方を対象とした後期高齢者医療制度がはじまりました。 |
国内居住要件の例外を確認する書類
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外を申告する場合は、「被扶養者申告書〔2面〕」及び渡航目的等を確認できる書類を添付してください。
また、外国語で作成された書類には、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳を添付してください。
| 例外該当事由 | 添付書類の例 |
|---|---|
① 外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② 外国に赴任する組合員に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 |
査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、②に掲げる者と同等と認められる者 |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ ①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
※個別に判断 |